Message
*寒の内の水は腐らない
日本人にとって桜は、ひときわ想いを寄せる花です。この花の色を染めるために、毎年試行錯誤をくりかえしてきました。散花では色が飛んでしまう。花の時期に先駆けての幹や枝をいためるのは忍びない。そこで気づいたのは、深紅に染まった葉。この落葉を集めてしっかり乾燥させて保存。年が明けて寒の入りを待って水を汲み、落葉を浸けこみます。数日後に、表面に浮いた葉を見ると、葉の色が抜けて、水の方に紅い色が移っていました。
これを漉した液を染料とし、低温から徐々に加熱して白絹を添えると、この時期ならではのほんのりとした桜色に染まりました。寒の内の水は腐らないという古くからの言い伝えは、今も生きています。
*いのちが輝くとき
ケルンの組紐子ども講座にシリアからの難民の少年が参加してきました。故郷アレッポの激戦地を追われ、安全なドイツに辿り着いたのです。見知らぬ国に来て、小さな物音にも怯える少年が子ども達の輪に入れるようになったのは4日目のことでした。「何てきれいにできたのでしょう!」と声をかけ手を取ると、言葉も通じてない筈なのに彼の表情がホッと和らぎ、夢中になってひもを組み始めました。ふと彼の後ろ姿を見ると、なんと座っている足の指先までが喜びでピクピク弾んでいるのが目に留まりました。幼な子の“いのちが輝くとき”を共にできることを、心から幸せに思ったひとときでした。
*草木を見る目が変わったヨッ
新学期になると、校庭に生えているナズナやハコベなどを摘んで染める体験学習をしていた地元の小学生に、偶然スーパーマーケットで声をかけられました。2年前に受講した男の子です。「あれから、どこを歩いていても、草木を見る目が変わったヨッ」と、笑顔で教えてくれました。草木がそれぞれ色を持っていることに、心を動かしたのでしょう!
*土に還り、命をつなぐクヌギの黄葉
今日は11月22日。二十四節気の一つ「小雪 (しょうせつ)」の節入り日です。朝の凛とした空気の中に、冬の気配が感じられる頃となりました。うすい陽ざしを透かして街路樹のクヌギの葉が黄金色に染まっています。光合成の役割を終えた葉は土に還り、やがて腐葉土となって土の中から樹を支える。樹の命を繋ぐ落葉は、終わりであると同時に新しい命のはじまりでもあります。実は、古くから茶染に欠かせない染料ですが、葉が色づくのを待ってしっかり乾燥させて染めると、冬ざれの幹の色になりました。
*伝統の流れの一滴
組紐は、1500年の歴史を持つ日本の伝統工芸です。1974年スペイン・バルセロナの専修学校から始まった組紐の海外コースは、ドイツ、オーストリア、スイスなど年月を重ねるごとに欧州で広がりました。その間には、成人、子どもコース、障がいを持つ子ども達の学校訪問,難民の子ども達のケアーなど28ヶ国、延べ3万人を超える人達に伝えました。振り返れば今年が国内60周年、海外活動は50周年を迎えていました。
先人から多くの教えを受けたからこそ、次の担い手を育てることができました。長い年月、手と手の伝達で受け継がれてきた組紐の流れの中の一滴となれればと、願っています。
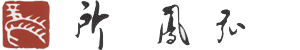
 日本語
日本語 English
English Deutsch
Deutsch Francais
Francais
 地域おこし
地域おこし